■道院を開くため神戸へ。実践稽古、梶原道全、そして圧法
昭和32年(1957)9月、森は自らの道院を開くことを決意する。場所は神戸。船に乗れば香川から一番近い港町である。とは言え、総本部の拳士の前で「神戸に骨を埋める覚悟でまいります」と挨拶してしまった手前、おめおめと帰ることはできなくなっていた。神戸に渡った森は、港湾労働者として働きながら、道院開設を目指した。恵光寺という寺に念願の道院を開設したのは昭和34年(1959)のことである。
道場を開設してしばらくして、ある空手の師範を名乗る人物がやってきたことがあった。その人物は、遠まわしに脅しめいたことを言った。「それは脅しか? なにしに来たんや」と森が問いただすと、「実は、自流派の五段の者が何者かにケンカでやられた。もしや少林寺拳法ではないかと思ってきた」と言う。そうは言っても、生徒はまだ7~8人。森を除くと白帯と、3級が最高位である。「まさか、五段の先生が3級にやられるわけもないやろ」と森は言い、「やったヤツ、おるんか!」と問いただした。「誰も返事をしない」。
それを見て空手家は帰ったが、後で、生徒の一人が、「実は自分がやった」と打ち明けた。当時の乱捕中心の実戦的な稽古が、短期間に生徒を鍛えていたのだ。
森は自分の戦いかた同様、弟子の背中に手を当て、下がれない状態にして乱捕を始めさせたという。下がらず、防御し、反撃できることが強さにつながると知っていたからである。
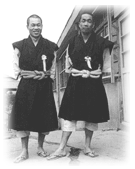 |
|
森大範士とともに「関西の三羽烏」に数えられた、故・梶原道全大範士(左)
|
森が影響を受けた人物に、神戸で先に道院を出していた梶原道全(故人)がいる。開祖、宗道臣の最古参にあたる高弟の一人であった梶原は「『少林寺拳法の字引』と呼ばれていた」と森は言う。つまり教範に載っている膨大な技を寸分もたがわず記憶していたというのである。「自分は、右足が前だろうと、左足が前だろうと、ちゃんと技がかかればいいだろう、というようないいかげんな感覚なんですが、梶原先生がそれを見ると、『それは違う』と怒るわけです」
森は、いかにも長年持ち歩いたことが偲ばれる、分厚い教範を取り出し、技の名が羅列されている箇所を示した。
「少林寺拳法の技も、初めからすべてができていたわけではなく、この赤い丸印がついているのは、後で付け加えられた技なんです。護身の技術ですから、状況の数だけ技が生まれるわけです。
『こうされたら、どうするんや』と質問される度に、開祖が新しく付け加えていったものが、実はかなりあるのです。ですから、技の基本さえ分かっていて、引っ張り出せばかなりの技が出てくるわけです。これにまだ圧法がありますから・・・」
柔法の一部に分類される圧法(押圧技)は、人体の急所(経路秘孔)を圧迫することで相手を制する技法であり、その威力の高さゆえに現在は高段者にしか教授が許されていない。圧法については、特別に講習があったという。「開祖もご存知で、急所(ツボ)を教えたし、圧法では坂東邦伯先生(故人)が有名でしたね。僕らもそれで急所の位置などを習いました。経絡のツボを圧法で攻めるわけです。気絶するツポに、たとえば水月がありますが、ここはよっぼどうまく攻めないと、相手が苦しむんです。水月は手首まで中に入ってしまうくらい突き上げないとかえって危ないですね。中途半端が一番いけない」
